はじめに:おこづかいってどう教えたらいい?
子どもに”おこづかい”を渡すのは
ちょっとしたワクワクの反面
親にとって悩みも多いテーマですよね
特に凹凸っ子の場合
「せっかく渡したのにすぐ使い切っちゃった!」
「欲しいものがあるときにお金が残ってない…」
そもそも(T . T)
ADHD児でもあるはるごんは…
呼吸をするように
お財布を紛失してきます(涙)

でも大丈夫!
工夫次第で「おこづかい」は
お金の使い方や社会を学ぶよい練習となります
今回は、おこづかい渡し方の工夫や
我が家で取り入れている
「おこづかい年俸制」についての考え方や
ルールをご紹介します
おこづかい制度の工夫:まずは短いスパンから
多くの家庭では
「月に○円」とまとめて渡す方法を選択していると思います。
しかしながら…
凹凸っ子にとって
1か月先までを見通すのは難しいことも
結果、最初の数日で気分に任せて
使い切ってしまうことが多いように思います
そんなときには
週ごとに分けて渡す方法がおすすめ♡
たとえば「1か月1,000円なら、毎週250円にする」といったイメージです
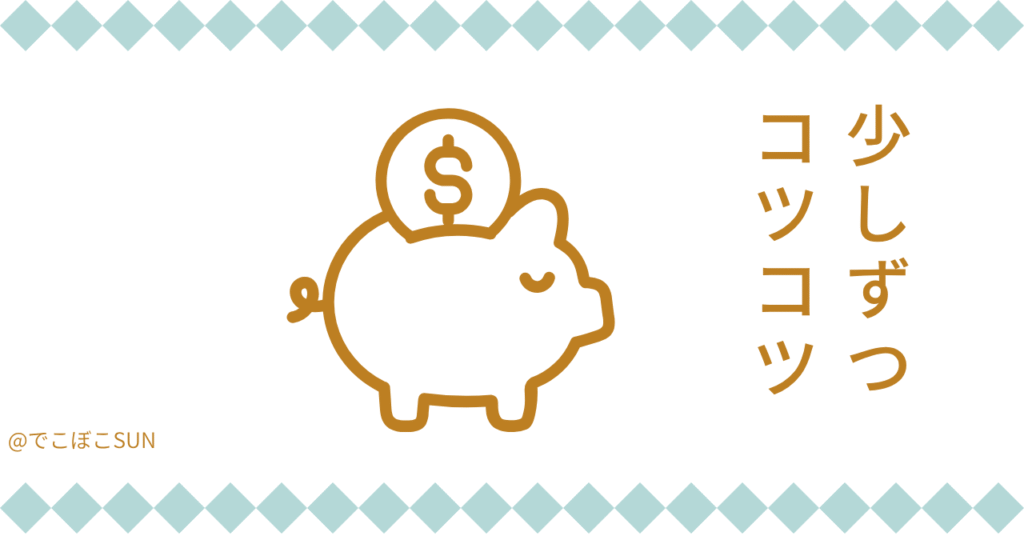
短い期間でやりくりを体験できるので
「次のおこづかいまでもう少しだから、残しておこうかな」
と考えるきっかけになります
また、「お手伝いをしたらプラス100円」といった形で
成果と結びつけるのも効果的です
お金は「タダでもらえるもの」ではなく
「行動とつながっているもの」だと実感できます
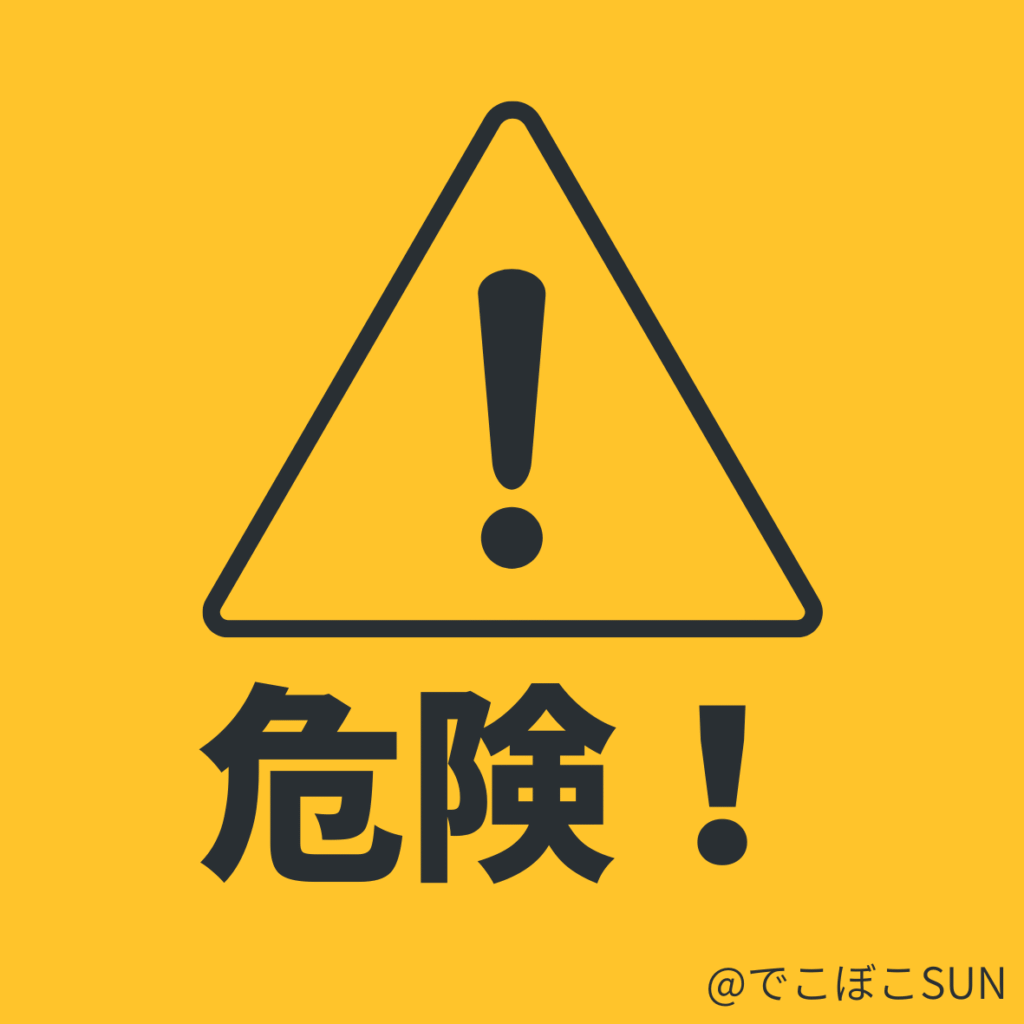
ご注意!
友人の失敗談を紹介しますね
お手伝いを労力とし
おこづかいを対価として提供していたところ
気がつけば
「配膳のお手伝いお願いしていい?」
「洗濯物いっしょにたたもうか」
「(愛犬の)お散歩に行ってきて」
ちょっとしたお願い事に対して
「やったら…いくらくれる??」
「50円ならやらない」
行動基準の全てが現金授受につながってしまい
賃上げの要望も甚だしい結果に…
導入時は、よかれと思い
子どもの社会訓練となるはずのママ銀行でしたが
あえなく破綻する運びとなりました。
幼さゆえの無謀さ…
おこづかい”対価制”を導入の際は
お気をつけください
年俸制の発想を取り入れてみる
我が家で実際に取り入れている「年俸制」をご紹介します
ビジネスやプロスポーツの世界でよく耳にする仕組みですが
「年間でいくら」と最初に取り決めし
その枠の中でやりくりしていく
おこづかいシステムです
これを子どもへ渡す、おこづかいに応用すれば
長期的な見通しを立てる力を備えることができます
たとえば「1年間で12,000円」と設定して
毎月の使い道を子どもに考えさせるのです
もちろん一度に大金を渡すのは危険なので
「年俸は決めるけれど支給は毎月申請制」
「余った分は次の月に繰り越せる」など
子どもの年齢にあった工夫を加えるとさらに安心です♡

ちなみに我が家では
12月下旬ごろから
翌年の年俸会議を開き、支給月は1月です
はじめにママから次年度の支給年俸を発表し
子ども達から”円満はなまるOK”を得られる年もあれば
“ちょっと待った!”のブーイングをもらう年もあります
ここからは子どもたちとの個別交渉になります
(主に賃上げ交渉です…)
テスト結果はイマイチだったけど
毎日の宿題や忘れ物なく登校できたので
もう少しUPしてほしい!
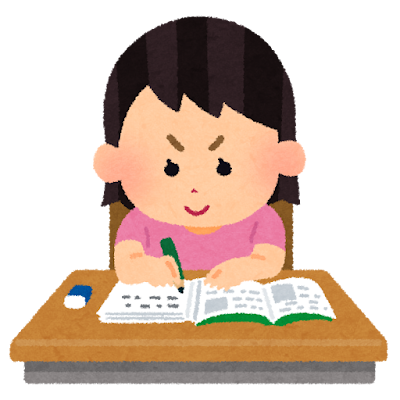
来年は持久走大会で◯位までに入賞するから!

次年度の期待値を交渉してくるなど
年々、巧妙になる交渉術ですが
子どもたちの成長を感じることができ
恒例行事として、これからもたくさん回数を重ねていきたいと思っています
凹凸っ子に合ったルールづくり
お金の管理が難しいと感じる子には
「見える化」がとても大切です
- お金を封筒に分けて「遊び用」「おやつ用」と色分けする
- アプリやノートで記録して、残りをグラフで確認する
- カレンダーにシールを貼って「次のお小遣いまであと何日」がわかるようにする
こうした工夫で「あとどれくらい残っているか」など
直感的に視覚から理解しやすくなります
それでも失敗はつきもの!
全部使い切ってしまったときには
「どうしたら次はうまくいくかな?」と一緒に振り返ることが
学びにつながります♡
叱るのではなく、一緒に考えることがポイントです
親の役割は「見守り役」
おこづかいを任せると
親としては
「全部使っちゃわないかな」
「ちゃんと考えてるかな」
と不安になりますよね
だからといって口を出しすぎると
自分で考える力が育ちません
おすすめは定期的な振り返りタイム!
月に一度おこづかい帳や
残っている現金を一緒に見ながら
「何に使った?」
「使ってよかったと思うのはどれ?」
などと親子で話しあってみましょう
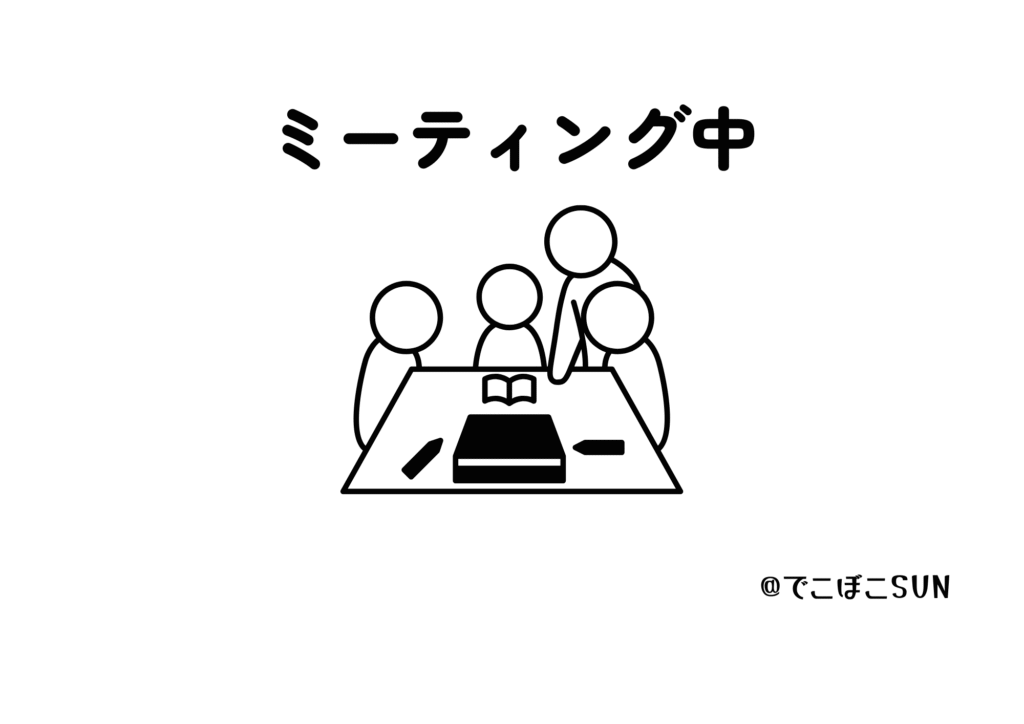
この時の保護者の立場は
“監督”としてではなく
“おこづかいの達人”として
見守り役に徹し、子どもと同じ立場で
ミーティングに参加してくださいね♫
この時間が楽しければ、楽しいほど
「お金について考える練習の場」につながります
実際にあったケース
はるごんの「年俸制」ケースですが、
あればあるだけ…大盤振る舞いしています
特に推し活グッズの購入時には、ブレーキが効かないようです
年に何度も一定の販売回数があるのですが
推し活ゆえに”今買わないともう二度と手に入らないかもしれない”
という焦燥感から、ついつい予算をオーバー気味…
母としていろいろ物申したいことは多々ありますが、
だまって見守りを継続
ここ数年は何度も…
下半期の推し活グッズ販売に参戦できず
涙を流しながら悔しい思いをしてきたので
最近は上半期と下半期に分けて
なんとか、おこづかい管理ができるように!
まぁ…管理といってもまだまだ詰めが甘い部分もありますが
ゆっくりと見守っていきたいと思います
ちなみに、学年の大きい上の子は
「年俸制」経験も長いだけあり
お財布から現金が”減っていくことの恐さ”を
実感できるようになりました
次年度に繰り越せる現金が”ゆとり”であることにも
同時に気づけたようです
まとめ:お小遣いは「自立への第一歩」
おこづかいは単なるお金のやりとりではなく
自立の練習になります
凹凸っ子にとって難しさも多々ありますが
週ごとのおこづかい制や年俸制の考え方を取り入れることで
無理なく金銭感覚を育むことができます♫
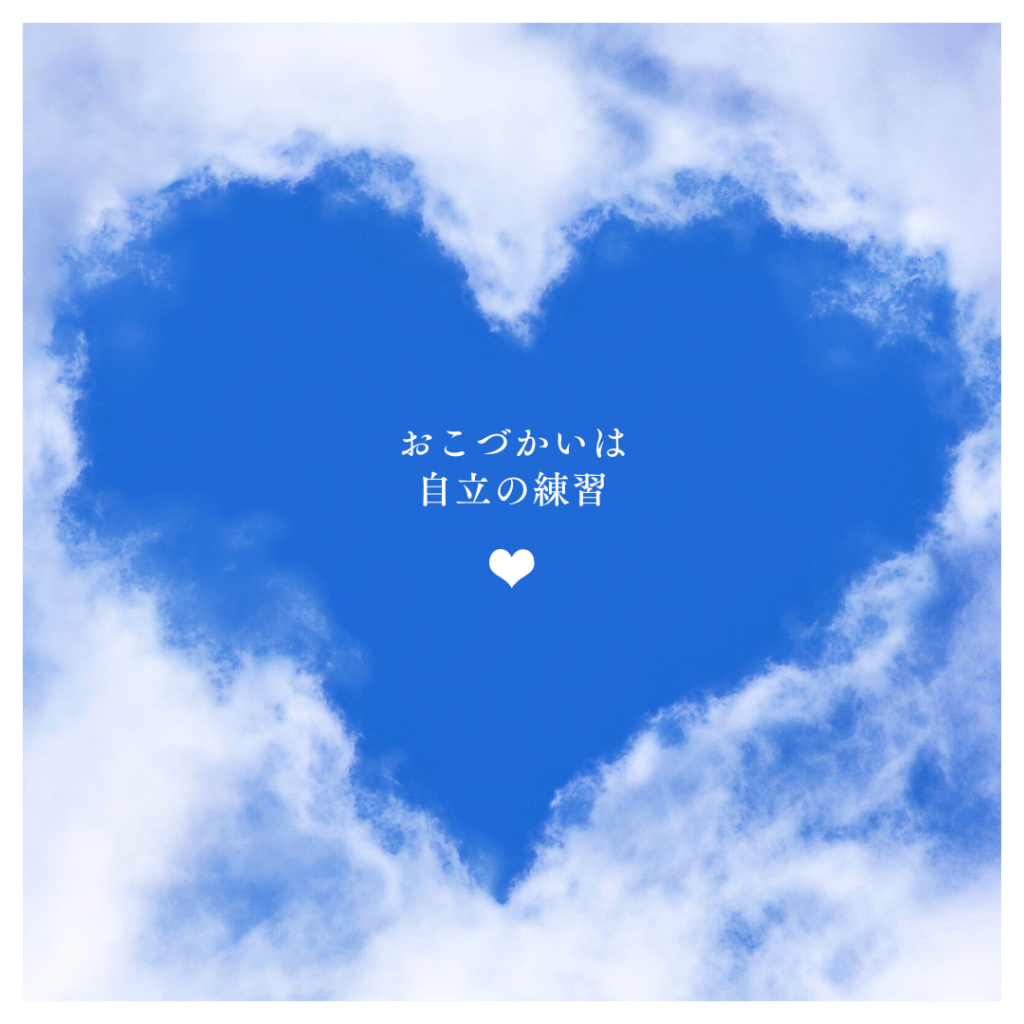
大切なのは、親が一方的にルールを決めるのではなく
子どもと一緒に考え
試行錯誤しながら
「その子に合った方法」を
見つけていくことだと思います
あなたのお子さんに合うおこづかいの渡し方はどんな方法でしょうか?
今日から小さな工夫を始めてみませんか(๑>◡<๑)

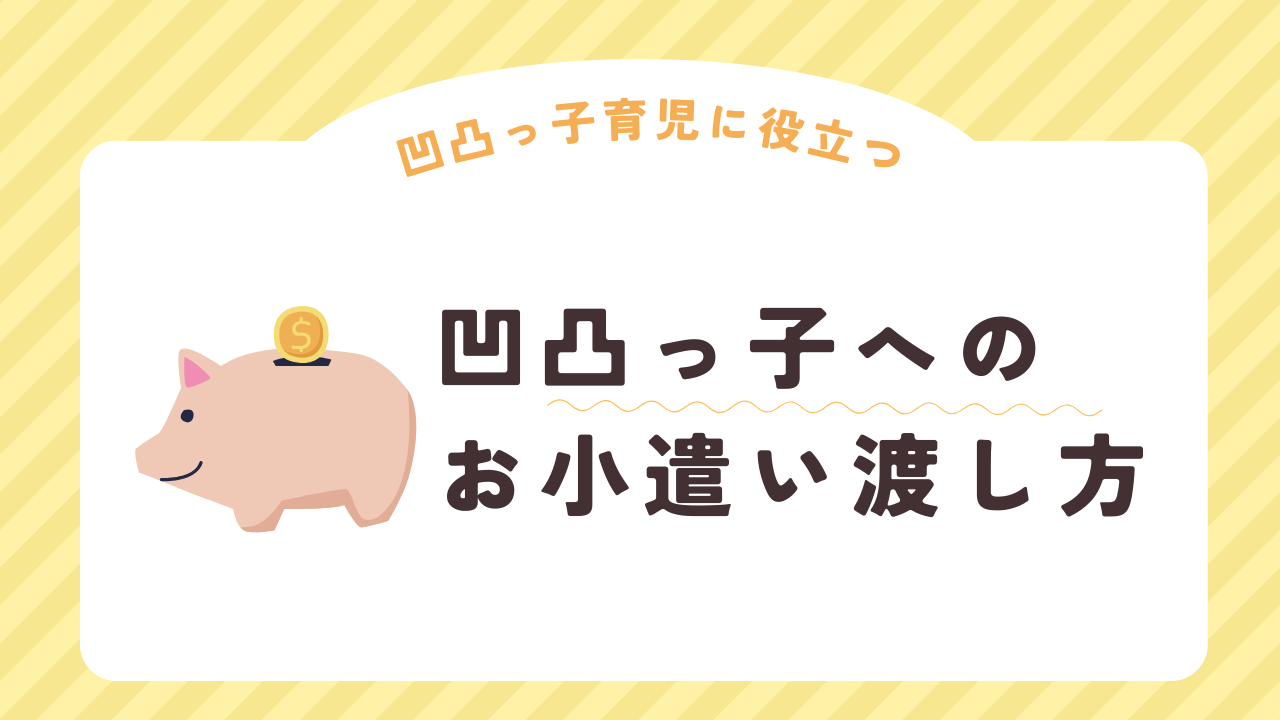


コメント